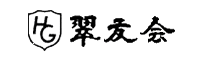広島在住者の皆さんはすでにご存知のことかも知れませんが、色々な偶然が重なって、原爆忌に、広島学院と縁が深いイエズス会神父関係の情報をお送りいたします。
情報源としての中国新聞社、広島平和記念資料館、それからお母様の手記公表で阿部優美さまから転載許可をいただきました。
これらの許諾に際して上智大学戦没者追悼の会の西村雅男氏にたいへんお世話になりました。以上明記し、皆様のご厚情に深く感謝いたします。
博覧強記で文字通り生き証人だったクラウス・ルーメル神父には、以下の書籍もあり、第一部「回想」に詳しく述べられていますので、ご一読をお勧めします。
赤羽孝久編『ルーメル神父の来日68年の回想』学苑社 2004.
*資料①中国新聞 2020/12/7朝刊「記憶を受け継ぐ」大沢美智子さん(91)「独神父のおかげ命継ぐ」
https://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=706592&comment_sub_id=0&category_id=256
*資料②「まえがき」阿部優美・「体験記」大沢美智子
*資料③ルーメル神父「日記」
豊田浩志 5期
***************************************
資料②「まえがき」阿部優美(大沢美智子の長女)
2019年11月24日に、フランシスコ教皇様が広島に来られることがきっかけで、同年11月12日地元新聞に「外国人神父たちの8・6(16人の手記や歩みを追う)」という記事が載りました。16人の神父様たちの当時の年齢、出身地、被爆場所・状況、その後などが丁寧に調べられて書かれていました。
私は、母からあの日、生き埋めになっていたところを外国人神父様に助けてもらったと何度も聞かされていたので新聞記事を丹念に読んでいきました。すると、二人の神父様が三篠橋付近(母が下敷きになっていた場所)で一緒に女児を助けたという記述がありました。フリードリヒ・タッペ神父様とクラウス・ルーメル神父様です。あー、この方たちに母は助けていただいたんだ、と感動しました。被爆後74年目にして、お名前がわかったのです。私はすぐに、近くに住む母の所へ行って記事を見せました。タッペ神父様はしばらくしてドイツに帰られ、若くして亡くなっていました。ルーメル神父様はずっと日本にいらしたのです。もっと早く何で探そうとしなかったのか悔やまれました。90歳になった母の一言は「会ってお礼を言いたかったねー。」でした。胸が詰まりそうでした。私の娘の一言も忘れられません。「ルーメル神父様がいらっしゃらなければ、私たちは存在しなかったかもしれないね。」本当にそうです。母には、娘2人、孫5人、ひ孫11人います。ルーメル神父様にお伝えできれば喜んで下さったのではないでしょうか?母を助けていただいたお陰でこんなに命がつながっているのです。
私たちは、興奮冷めやらずでしたが、お名前が分かっただけでも奇跡ではないかとさえ思いました。
そして、その約一週間後、11月18日に同じ地元新聞に「被爆神父 十字架を残す」という記事が載りました。上智大学のフランツ・J・モール神父様とルーメル神父様の交友について書かれていました。そして、なんと、ルーメル神父様は、死去の直前に「被爆日記」の存在を明かし、モール神父様にその日記を託されたという内容でした。8月6日のルーメル神父様の日記が引用されていました。「三篠橋近くで家屋の下敷きとなっていた母と娘2人を救出した。夫は死んでいた。三人の言う事、その時の気持ち忘れられない」というものでした。まさに、母たちの事でした。モール神父様は、その日記を広島平和記念資料館に寄贈されたとのこと、それが、資料館に展示されていることを知りました。私は、矢も楯もたまらず資料館に行きました。
ルーメル神父様の日記は確かに展示されていましたが、ガラスケースの中で開かれていたページは8月6日ではありませんでした。私はすぐ資料館事務室に行って事情を話し、8月6日のページを読みたいと伝えました。担当者様も驚かれて、異例ですがと前置きして前後のページをコピーして下さいました。
そこには、克明に母たちの救出劇が書かれていました。母たちは、8月6日午前8時15分に、一瞬のうちに家屋の下敷きになり身動きできなくなっていました。その後12時間以上生き埋めのまま、息も絶え絶えになっていました。
日記を読むと、神父様たちは、自分たちも被爆しながらも、積極的に救護活動をされていました。ルーメル神父様も、市内で活動を終えて夜、長束教会に帰られました。が、ほっとする間もなく、幟町教会の神父様の救助を頼まれ、再び出かけられました。その途中で三篠橋(母たちの家)を通りがかられたのです。
原爆が落とされてからすでに12時間も柱などに押さえつけられていた母たちは声を出す気力もなかったようです。しかし、末っ子の娘(私の母、当時15歳)を思う親心か、母親(私の祖母)は、「助けて、ここに若い娘がいます。」と必死に声を振り絞っていました。その声は、中々気付いてもらえません。屋根の上を人々がうめきながら歩いていく音はしたそうです。そんな中、ルーメル神父様は、「どこからか、声がする。あの大きな家の下からだ」と、か細い母親の声に気づいて下さったのです。そして、時間をかけてまず娘二人をがれきから救出しました。そんな中、ヨハネス・ジーメス神父様に会ったルーメル神父様は、まだ下敷きになっている母親を助けてからジーメス神父たちに合流すると言ったそうです。
そのジーメス神父様の日記には、次の日ルーメル神父様に頼まれて、河原に寝かせたままの三人の様子を見に行ったが、もう三人はいなかったとあります。さぞかし、ルーメル神父様は、その後三人がどうなったのか気になさっていたのではないでしょうか?
1987年に撮ったビデオが国立広島原爆死没者追悼平和祈念館に残されています。ルーメル神父様はそこでも母たちの救出劇を語っていらっしゃいます。その後助けていただいた3人のうち、結局生き残ったのは私の母だけでしたが。
あの時、ルーメル神父様が、倒壊家屋の下からの微かな助けを求める声を聞き逃さなかった奇跡に感謝します。
^^^^^^^^^^^^^
体験記
大沢(旧姓・吉川)美智子
「足が立つようになるんなら生きてもええが、このままなら死んだ方がましじゃ、何のために長い間苦労してきたんか分かりゃあせん」と母はいつも言うのでした。子どもを育てたからといって子どもの世話にはならないといって、私たち兄弟姉妹7人を育てた母だけに、母の心を察すると気の毒でなりませんでした。和服仕立から、後には綿や布団の商売を始め、厚い信用を得た苦労の果てが原爆という十字架であったとは。
私の生家は平塚町でしたが、1945年の3月中頃県庁から、明日の12時までに立ち退くようにと通達がありましたので、私たちは取りあえず差し向いの家の2階を借りて家財を運びましたが、その家も建物疎開になり、7月20日、三篠橋のたもとの家に移転しました。ここは二階だけでも畳24枚敷ける大きな家で、西側の庭は川に面し、晴々とした光景にやっと落ち着いた気持ちになったのでした。
8月6日の朝、東京からお産のため帰っていた姉夫婦と母と私の4人が茶の間で朝食を終え、丸いお膳を囲みお茶を入れて義兄の面白い話に口を大きく開けて4人がどっと笑った時でした。ボッと電気の爆発のようなものが、裏庭に落ちたのです。アッ助けて!と言う間に、私たち4人がばらばらに吹き飛ばされるのと、家が崩れるのと同時でした。気がつくと、仰向けになった私の上には大きな柱や壁が2階の梯子と一緒に落ちてきていました。腹の上には大きな柱が横たわり、顔すれすれに崩れた壁、重なる柱、板、瓦。2階の重みが全部私にかかっているような気がして、腹を中心に上下に引き裂かれるのではないかとさえ思いました。姉も私も母を呼びましたが義兄の声がありません。それに気づいた姉は主人の名を呼び続けましたが返事はありませんでした。声のみ聞こえる3人は息があるというのみで、母も姉もうつ伏せに、骨が砕ける位押さえられていたのです。姉はお腹の胎児が動かなくなったと泣いていました。同じ状態で弱り果てた母が、「可哀そうに」とだけ言いました。
ぱちぱちと燃える音と一緒に臭い煙が這ってきました。私ははあはあ息切れがし、苦しくなりました。壁の土は崩れ落ちて私の眼や口や耳に入りますが顔を横に向けて防ぐこともできません。腰から下はとうとう血が通わなくなったのかしびれて痛みが少なくなりました。
時々瓦をミシミシと踏んで行く人の気配、道路や橋のほうで女や子どもの叫ぶ甲高い声、ウーンウーンと近くでうめく人の声、水をくれ水をくれと断末魔のような声、外の見えない私は自分の家が直撃を受けたのかとも思いました。しかし何時間経っても誰も助けに来てはくれません。苦しくて恐ろしい時間、それは長い長い時間でした。日が暮れると心細さが苦しさと一緒になって死の恐怖を誘い、このまま死ぬのかしら、明日まで生き延びることができるのかしら、親せきのものが助けに来てくれないかしら、と思いつつ当時、16歳の女学生の私は、今まで想像もしなかった現実の死に直面し、それでも死にたくないと思いました。「お母さん、お母さん」と叫ぶと、母の返事は5回に1回くらいやっと聞こえる程度。母も姉も死の一歩手前、虫の息のようでした。
下敷きになって17時間余り、意識もなくなりかけた頃でした。「ココデスカ、ココデスカ?」という異国人の声にハッと意識を取り戻した私は、嬉しいとも悲しいともつかぬ気持でした。ガタガタと柱などを取りのけてゆく音もうつろに響くだけでした。大分経って「こんな建物の下ではとても出せんかもしれんの」と絶望的な言葉に、母も姉も「私たちはどうせ出しても助かりません。このままにしておいて下さい。けれども美智子だけは、もう一度生かしてやって下さい」とかすかに言ってくれているのが聞こえました。異国人というのは当時近所の教会にいたドイツ人の牧師さんでした。牧師さんは田舎から救助に来られた警防団の人たちと一緒になって、やっとの事で私たち3人をひっぱり出して土手の道端に寝かせてくれました。その時牧師さんがいいました。「神様のお陰です。手を合わせて祈りなさい。たくさん、未だ助けられない人たちがいます。どうしようもないのです」暗い夜空に遠く、福屋デパートの6,7階の窓という窓からパッパッと火を吹いているのが異様に見えました。それから間もなく夜が明けました。よく見ると私たちの家の周り4,5軒だけが火災を免れただけの焼け野原。
私たち母娘は動けない体を道端に転がされていました。そのそばには第二部隊の兵隊さんがたくさんいました。顔は黒くなって風船のようにふくれ、唇は大きく裂けたり膨れたり、しかも皆同じ顔で背の皮も胸の皮も厚くめくれてぶら下がっているのです。指1本1本の皮も皆ぶら下がって、5本の指を広げて突っ立っていたり、転げたりうめいたりしていました。真夏の日がだんだん高くなって陽が射すと痛いのか汚れた毛布を被っていました。私たちの前を歩いて逃げる人たちも黒く焦げ、唇は裂けて、黙々と進んでいました。
救助の赤十字軍は死体を運ぶのに忙しく、息のある私たちは中々運んでもらえそうにありませんでした。昼過ぎに親せきのおじさんが馬のいない荷馬車を拾ってきて、私たち3人をそれに乗せ、戸坂の、ある納屋に寝かせてくれました。しかし一滴の果汁もなく、一滴の傷薬もなく、蒸し暑さに拍車をかけられた傷はみるみる化膿して膿が流れ続け、高熱とともに烈しい下痢が続いても、這うことさえできませんでした。姉のお腹の中で死んでいた胎児は、8日朝産まれました。お医者様も産婆さんもきてはくれません。隣の家でも裏の家でも逃げ延びて帰ってきてはばたばたと死んでいくのだから、だれも助けにはきてくれないのです。姉は死んでいるとは思えない丸々とした赤ちゃんをじっと見入っては、この子の父親をしのんでか、ぽろぽろと涙を流すのでした。そして姉は数か所も腐っていく体で、後産の出ないまま、何時間もあえぎ続けるのです。なんというみじめな姉の姿だったでしょう。重傷にあえぎつつも後から後から溢れ出る涙は、血と泥に汚れた私たちの顔をいつまでも濡らすのでした。
二、三日して、栃木にいた姉と横浜にいた姉が炎天の中を天蓋もない貨物車でかけつけてくれました。私たちの変わり果てた姿を見て、声をたてて泣きました。それから二人の姉の必死の看護が始まったのでした。それでも傷ばかりはどうすることもできず、九州の救助隊の兵隊さんがリバノールを少し塗っては帰るだけで、傷は膿み放題でした。母は額の半分の肉がそがれ、頭の骨が露出し、右手の内側は中の骨が見えるまで肉が崩れ、両足の付け根も、押さえられたらしく大きく肉が取れて紫になって腐り、膝坊主のところの2か所の傷が、どちらも深くなって両方からトンネルになっていました。姉の傷はそれ以上にひどかったのです。
二週間くらい経ったころ、ようやくこの村の小学校が病院になって重傷患者だけを収容していることを聞き、私たち母娘もそこへ入ったのです。手術といっても麻酔薬もなければ、ただ鋏とメスで肉を切り取るだけで芋の黒く腐った所をほじくり取るのと何ら変わりません。医者は手荒な軍医さんのみ、特にひどい母の右腕は全部切り落とすよう言われました。私も腰の膿肉を切り取って貰うときは気を失ってしまいました。それでも、あれほど痛かった私の傷は三人の中で一番軽かったのでした。
その頃私たちの居た病室は十人以上の患者がいました。部屋の片隅で苦しい苦しいと叫び続けて狂い死にした若い女性は、焼け崩れた顔も体も女性とは思えぬ凄さで、毛布にくるまった体の傷から蛆が這い出ていました。また、私の隣に寝ている女学校の一年生は、顔から胸、腹、足の先までずるむけの赤身になっていて、はあはあと言いながら流動食を飲む口がかすかに開くのみで、苦しさと痛さのあまりに痛い痛いと泣き叫ぶのでした。それも間もなく亡骸と変わり、また新しい重篤患者が入ってくるのでした。そして今日は隣の人、明日は前の人がとぞくぞく亡くなりました。半分以上が死体となって消えた頃、次の村の矢賀小学校に移動することになり、残暑厳しい9月の初め、他の患者とともに炎天の中をトラックに寝かされて矢賀にきました。ここでも口が焼けただれ、一緒にくっついて、開かなくなり、唇の上の穴から流動物を流し込んでもらっている人など眼を覆う重い患者ばかりいましたが、それもまた一カ月経たないうちに過半数が死体となってしまったのです。その度ごとに、次は母か姉か自分かと死の恐怖に怯えていました。
こうして9月も過ぎ10月のわびしい秋ともなり、各病室もひときわ淋しくなりました。母と姉は依然として下痢が続き、姉の足は手術して切り取ったにもかかわらず、肉は腐り膿が流れ、足の奥深くまで骨が透けて見える位になっていました。床ずれは大きくなり苦しさはつのるばかりです。10月半ばころ、初めて外科専門医が来られ診察されるや否やもう一度手術し直さねばならないと言われ、弱り切っている姉は再び手術台に上ったのでした。しかし、姉は手術後間もなく敗血症を起こし、高熱が出て毎夜毎夜苦しみ続けました。「私は生きる価値はありません。主人に死なれ、子どもに死なれ、何の望みもありません」と姉は涙ながらに言って、ローソクの灯揺らぐ秋の夜にこの世を去ったのでした。術後10日目のことでした。
母の傷は未だ癒えず、手足の神経は深い傷のため切れて自由にならず、下痢は一日として止まらず、蒼白な顔を見ると不安でたまりませんでした。11月、12月、とうとう吹きさらしの学校の病室で寒い正月を迎えました。その頃から母の傷もようやく癒えて窓にもたれて立たせてあげるようになりましたが、片手片足の不自由な母をみると気の毒でなりませんでした。私は歩けるようになり、母も傷の治療だけは必要なくなったので、一人の姉と私と母と三人、白島の親せきに部屋を借りることになりました。そこは焼け残った煉瓦の暗い部屋で、窓ガラスもなく、寒さにふるえて冬を越したのでした。
4月、江波の元陸軍病院内にあるバラックに移り住むことになりました。その頃から母はトイレくらいには足を引きずって行けるようになったのですが、白血球はますます減っていき、その上栄養失調で体は骨と皮になるばかりでした。7月になって漸く兄が復員し、姉も嫁ぎ先へ帰っていき、母と兄と私の生活が始まりました。被爆まで病気一つしたことのなかった母の体は痩せて青くなり、足がむくれてきました。時が経つにつれ、食欲はなくなり下痢が始まり、足のむくれもひどくなり節々に水がたまるようになって、その痛みは我慢強い母も叫ばずにはいられませんでした。何とかしようと思っても、原爆で何もかも失くした私たちは、働かねば食べることもできず、私と兄はお金を稼ぐことに懸命でした。母は、どこのお医者さんも原因がつかめず、体の衰弱と白血球破壊、それにともなう心臓病だろうと言われました。衰弱は増すばかりでした。医師はもう助からないと言いましたが、兄は医師にリンゲル注射をお願いしました。とても助からない母にこの上の苦しみを見ることは私たちには堪えられないことでした。けれども私たちは何物を売っても母の注射液を買うことに夢中でした。そして奇跡が起きたのです。どうにか命だけは取りとめることができました。さじを投げた医師も驚いていました。どの医師もはっきりした病名を言うことはありませんでしたが、結局は白血球の破壊が一番影響していることは確実で、寝たままなのに目が回るといった具合でした。母は長い病床に手を煩わす私たちに気の毒がって、一日も早く死ねる日を待ちわびているのでした。寝たきりの体で、しかも痛みにうめく毎日に、生きるということが苦痛なのでした。それでも「美智子が結婚するまでは生きていたいよ」と口癖に言い、その言葉が母の命を延ばしているようでした。
何もかもが悪条件に侵されつつ、幾度も死の危機をくぐり、奇跡の命を重ねた母は、立ちかえる平和もよそに身も心も蝕まれながら過酷な運命に呻吟しつつも死と隣り合わせの状態で、被爆後11年目、やっと楽になったのでした。再びこの運命に陥る人のないことを切に願って やみません。
______________________________
資料③ルーメル神父「日記」

クラウス・ルーメル神父
P.Klaus Luhmer,S.J.
略歴
1916.9.28 ケルンに生まれる
カトリック少年運動での活動とともに、ヒットラー・ユーゲント入隊
1935. 4.26 イエズス会入会
1937. 2.17 来日
1945. 7. 1 司祭叙階
1945. 8 .6 広島市郊外のイエズス会長束修錬院(爆心地から4キロ)にて被爆
1956~57 東京大神学院院長
1957~65/1984~88 SJハウス院長
1958~65/1987~92 上智学院理事長
1977~2007 日本モンテッソーリ協会会長
1996~2002 社会福祉法人友興会理事長
2011. 3. 1 ロヨラハウス・武蔵野赤十字病院にて帰天
以下のスケッチ画は、神父自筆の日記とともに、広島平和記念資料館に展示されている。

(左下メモ) 昭和20年8月6日正午頃、広島市祇園町の旧国道を原爆被災者をリヤカーに乗せて救護所に向かう2人の外人を目撃した。其の後、昭和51年10月、外人の1人、K・ルーメル先生と判明した。当時先生が御活躍された善行に敬意を表する意味で、それを回顧して絵となす。
(右下メモ) スケッチ作者の下村氏自身が描かれており、“私(下村儀三)は可部町より歩いて己斐の自宅に帰る途中です” との但し書きがある。
以下は、1945年8月18日にルーメル神父が8月6日の原爆投下後の被爆者の様子と救護活動を記録した自筆日記からの抜粋。
1945.8.18
6日以後日記を書き続ける時間もなくて、其間経験した事が餘りに恐ろしいので書く気分も起こりませんでした。
6日の朝8時ちょっと後の事ですが、広島市の上に物凄い幅の広い大きな炎が現われた。これこそ長く前より予想して居た空襲だなと思って、私は地下室への階段に飛び下りてしまいました。と同時に間もなく音の深い爆発が聞こえ、家が震え、窓ガラス等色々なものが私の頭の上にどたんと落ちてきます。
再び頭を上げますと、最早村の農家あっちこっち燃え上がって居ます。そして広島市の空は真黒になって居ます。私達皆たくさん血を流して居ますが、誰も大きな怪我をして居ません。
しばらくして町より最初の火傷した負傷者が非度く泣きながら走って来ます。苦しがって呻きながら聖堂、応接間等で横になります。一番悪い患者を祗園の救護所へもって行きます。帰り道に長い長い負傷者の行列を通らなければならない。一日中続いて後から後からと人が走ったり、泣いたり、さけんだり、大火事の中より逃げて来ます。火傷は普通の火傷でなく、医師も初めに療法を知らない。アルペ院長様も朝から晩まで、又晩より朝まで治療に忙しいです。
6日の夜、疲れ果てたにもかかわらず、幟町教会からラッサル神父様を担架に乗せて以て来る人を迎えに行きます。三篠橋でしばらく待つと兵隊の叫び声が聞こえ、水、水と言って居ます。何十人非度く火傷した人が燃えて居る兵舎の側に横たわって居ます。近くの井戸より水をたくさん汲んで来ると、近くの倒れた家の上に人がやって来て「向うに病人が居るらしいから少し見に行って下さいませんか」と云って見えなくなってしまう。
行って見ると、遠くより「助けて、助けて」と叫ぶ声がある。しかし方面が解からない。しばらく良く聞いてから、この声が下より、二階の家の下に下敷にされた母と二人の娘より発せられるものだと解った。其の場で二人を掘り出して、後の一人を警防団にまかせて置きました。
一生の間その三人の言う事、その時の気持忘れられない。一人の胸の上に重い板が落ちて、一日中その胸を押付けて居た。もう一人はちょうど孕んで居た。若い主人は直ぐ側に死んでしまって居た。
それから幟町へ行き続きまして、途中で見たあの大火事に照らされた景色を描く事が出来ません。破壊、死人、死にかかっている人間…。
後で聞きますと、最初に死んだ人間だけで20万ばかり死んだ。その他の90パーセント以上は負傷したが、後で其の大部分は救護所の中に死亡した。
1945.08.15 日本降伏。29才
――― 翌日16日に司祭になって初めての葬式ミサを行った。――――
1945.8.24 帝釈にて
この10日間の間見た有様を描く事が出来ません。何回も死と云うものの一番恐ろしい姿に出合った。
それから聖母被昇天の日天主はいよいよ足れりとお思いになり、急に、誰も考えなかった所に平和となりました。しかし私達は未だこの平和の為の最後の犠牲を葬らねばならなかったのです。最初にやられた20万人の外に火傷した可愛想な人間は後から後からと死んでしまいました。これらと合わせて死亡者の数は30万に達するだろう。
16日の朝、教会の隣組の中で亡くなった人の為葬儀ミサを歌いました。各々の家族に死亡者一人、二人、三人位おりました。これは私の最初の荘厳葬式御ミサにして、この時の説教は司祭になってからの最初の私の説教であった。この大戦争の猛烈な最後の一時期は即私の司祭生活の最初の一時期であった。……
現在から見れば過去のこの二週間は夢の如く思われます。メルヘンの世界にでも這入ったかのような気が致して居ります。今住んで居る家はおとぎ話に出てくるお城の様に湖の中に立って居ります。天主様御自身が不思議に我等を慰めて下さいます。
平和になってからでも警察は軍部の騒乱を恐れて、この世を離れた所に移動する命令を発した。6日以後の事永久に忘れられなくとも、いくらかこの静寂なる所に落ち着く事が出来ます。
主よ、汝の平安を我等に与え給え! (自筆日記のコピー)

(以下は上記の「ルーメル日記」の後のドイツ語1頁分の和訳)
現在私を囲んでいる雰囲気には、平和が香っている。この平和は、人間の戦いと争いに汚されていない、神聖なる真の自然である。
私の居室の窓の前では、蒼い湖の波が険しい崖に当たっている。森がある丘の上に青空が広がり、白い雲は丘を越えて流れていく。
これは、美しい響きに満ちた歓呼の歌のようにも聞こえる。この歌を創造主御自身が歌い出され、我々も一緒に歌うように招かれている。
我が魂よ、ここ帝釈峡で憩っていて良いのでしょうか?ほんの少し前に体験したあの全滅と、ひどい狂乱の破壊力から快復するために・・・。
傷ついた可哀相な心よ、ここで安らぐことができるだろうか、受けた傷が治るだろうか? とてつもなく恐ろしい体験、何万人が死んでいった惨状をこの目で見たのだけれど。
いつまでも、このこと―原爆投下―は忘れないだろう。生きながら埋められた人々と、その骸を埋めた者たちと、生きながら焼かれていった人たちの苦しみを、熱い鉄筆で魂に刻んだのだから。
今から永遠に、それにもかかわらず、自分自身の中で改めて思い起こしても良いだろう。すなわち、憎悪と苦難と死とは、神様が作られたこの世界の一面のみ描いている。他面には、平和と喜びと調和が描かれている―この側面のために生きることにこそ、価値がある。
上智大学講師、篠田愛理・記
クラウス・ルーメル神父は、原爆投下直後の広島市民の惨禍や救護活動の詳細を日本語で、縦書き、旧仮名遣いで日記帳に残しておられた。
この「ルーメル日記」(1945年8月中旬)の後に ドイツ語で書かれた頁があり、
2012年にそれを マウツ上智大学教授(ドイツ語学科)がタイプ。ルーメル神父の教え子の江島正子教授(モンテッソーリ教育)と、長町裕司神父(神学部教授)がその部分を2013年に和訳した。(著作権 F.モール名誉教授)
日記本体はイエズス会から広島の平和記念資料館に2011年夏永久寄贈された。
†ルーメル神父の誕生日は1916年9月なので、1945年の原爆投下当時は、繰り上げ叙階されて間もないまだ28歳の若い司祭だった。
「ヒトラー・ユーゲント」に入隊したのは、当時台頭してきたナチズムから身を守るため。 ナチスが敵対視していたのは「ユダヤ」「フリーメーソン」「イエズス会」であった。 ルーメル神父はカトリックの少年運動の地下組織的活動を続けながら、こちらでも積極的に活動をし、信用されるよう努力した。
徴兵検査前のルーメル神父の日本派遣には ブルーノ・ビッテル神父が「日本の上智大学はドイツの文化を教授する大学であり、ドイツ人を必要としている」とドイツ軍部を説得したことで、可能になった。
ルーメル神父の日記の旧かな遣いや旧書体での漢字について、誤字の修正を含め、神父の文体を活かしながら一部修正を行った。